アルコールチェックの運用ルールと運用事例|確認方法や記録項目・罰則などを紹介
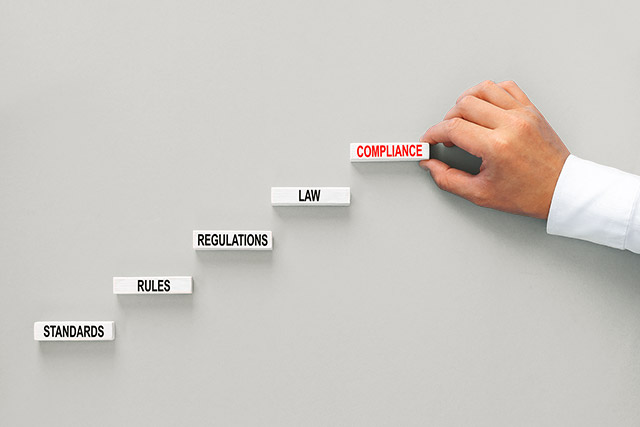
2023年12月から義務化されたアルコールチェッカーを用いた酒気帯びの有無の確認(アルコールチェック)は確実に実施できていますか?
アルコールチェッカーを導入したら義務化に対応できている、というわけではありません。
- 社内での運用構築ができているのか不安
- いつアルコールチェックを行うのかわからない
- どのような記録を残さなければならないの知りたい
このような不安や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、アルコールチェックの運用ルールや記録方法について詳しく解説します。
目次 / この記事でわかること
1.アルコールチェックの基本運用ルール

まずは、アルコールチェックの基本運用ルールについて、以下の4つのステップにそって紹介します。
- ①安全運転管理者を選任する
- ②アルコールチェッカーを導入する
- ③アルコールチェックの運用を社内に周知する
- ④酒気帯びの有無を確認(アルコールチェック)・記録する
①安全運転管理者を選任する
アルコールチェックを行うためには、まず安全運転管理者を選任します。
そもそも、アルコールチェックを実施しなければならないのは、下記のいずれかを満たす事業者です。
- 白ナンバー車両を5台以上保有している事業所
- 乗車定員が11人以上の車両を1台以上保有している事業者
2022年4月から、安全運転管理者の業務内容として、以下の業務を行うことが義務付けられました。
- 運転者の運転前後の酒気帯び確認
- 酒気帯び確認の結果を1年間記録保存
そして、2023年12月からは
- アルコール検知器を用いた酒気帯び確認
- アルコール検知器を常時有効に保持
も義務付けされました。
副安全運転管理者の選任は必要?
副安全運転管理者は自動車を20台以上保有している場合に選任が必要です。20台増えるごとに、1人を追加選任する必要があります。
関連記事:『安全運転管理者とは?選任義務から罰則、業務内容まで詳しく解説』
『副安全運転管理者は必要?資格要件や業務内容について徹底解説』
②アルコールチェッカーを導入する
執筆時点(2023年7月)では、白ナンバー車両を保有する事業者は、アルコールチェッカーの導入は必須ではありませんでした。
しかし、2023年12月1日からアルコールチェッカーを用いた運転前後のアルコールチェックが義務化となりました。詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
『【2023年12月1日開始】アルコールチェック義務化の対象と対応すべきことを解説』
目視等での酒気帯びの確認には限界があります。また、虚偽の報告や運用の形骸化に繋がりかねません。そのため、アルコールチェッカーの導入が推奨されています。
2023年12月から義務化されたアルコールチェッカーを用いた酒気帯び確認を遵守するためにも、アルコールチェッカーを必ず導入しましょう。
なお、アルコールチェッカーは導入して終わりではなく、常時有効な状態で保持しなくてはなりません。アルコールチェッカーの定期的な点検も必ず行い、アルコールチェックを確実に運用できる体制を整えましょう。
おすすめのアルコールチェッカーは?
おすすめのアルコールチェッカーは、クラウド管理型のアルコールチェッカーです。リアルタイムで検知結果が確認できるため、直行直帰で管理者が目視で確認できない企業には特におすすめです。
また、アルコールチェック対象人数が多い企業からしても、膨大な検査結果をクラウド上で管理できるため、管理の手間が省けるメリットがあります。
数あるクラウド型アルコールチェッカーの中でも、「アルキラーNEX」はさまざまな機能を兼ね備えています。これからアルコールチェッカーの導入や切り替えを検討している企業は、ぜひご検討ください。
また、以下の関連記事では、アルコールチェッカーを3タイプに分類し、それぞれのおすすめアルコールチェッカーを紹介しています。ぜひご覧ください。
関連記事:『アルコールチェッカーを機能や使用目的ごとに比較!おすすめの10選』
③アルコールチェックの運用を社内に周知する
アルコールチェッカーを導入すればすぐにアルコールチェックの運用ができるわけではありません。確実にアルコールチェックを実施できるように、企業ごとで運用ルールを定めて、全従業員に周知する必要があります。
決めなければいけない項目としては、以下などが挙げられます。
- 誰がどのように確認し、どうやって記録を残すのか
- 安全運転管理者が不在時は誰が責任を持つのか
- アルコール反応が出てしまった際の業務はどうするか
これらの運用ルールを事前に周知してから、運用を開始するようにしましょう。
④酒気帯びの有無を確認・記録する
ここまで準備が完了したら、実際に酒気帯びの有無を確認(アルコールチェック)・記録します。
原則として対面で、運転者の顔色や呼気の臭い、応答の声の調子等で酒気帯びの有無を確認します。アルコールチェッカーを導入している場合は、この際に確認しましょう。そして、確認した内容を記録します。記録の保存期間は1年間です。
アルコールチェックを実施するタイミングはいつ?
アルコールチェックを実施するタイミングは、運転前と運転後の1日2回です。1日に数回運転をする場合は、運転の都度行う必要はありません。
対面で目視確認できない場合はどうする?
勤務場所に直行直帰するため対面での目視確認ができない場合は、運転者に携帯型アルコールチェッカーを携行させます。そして、カメラ・モニター等によって運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコールチェッカーによる測定結果を確認する方法で行います。
2.アルコールチェックの運用において記録が必要な項目

アルコールチェックの運用において確認・記録が必要な項目は、以下の8つです。
| 1年間記録・保存が必要な8つの項目 |
|---|
| ① 確認者名 |
| ② 運転者名 |
| ③ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 |
| ④ 確認の日時 |
| ⑤ 確認の方法 |
⑥ 酒気帯びの有無
|
| ⑦ 指示事項 |
| ⑧ その他必要な事項 |
上記の具体的な記録方法については以下の関連記事にて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:『アルコールチェック記録簿|項目や記入例、クラウド型検知器で簡易的に実施する方法を紹介』
3.アルコールチェックの運用を効率化する3つの方法

アルコールチェックの運用を効率化させるために必要な3つの方法を紹介します。
① アルコールチェックの体制・フローを整備する
アルコールチェックの運用を効率化するためには、アルコールチェックの体制・フローを整備することが大切です。具体的には、アルコールチェックを行うタイミングや確認方法、アルコール反応が出てしまった際のルール等を定めます。
そして、定めた運用ルールを全従業員に周知させ、体制を構築しましょう。
② 運転者への周知・教育を徹底する
アルコールチェックを効率化するためには、運転者への周知・教育の徹底が欠かせません。アルコールチェックを行うタイミングやルール、アルコールチェッカーの使い方などを周知させることが大切です。
また、アルコールチェックを怠ったときや、万が一アルコール反応が出てしまった際に発生する影響についても、きちんと説明しておきましょう。
③ クラウド型のアルコールチェッカーを導入する
そして、アルコールチェックの大幅な効率化に繋がるのが、クラウド型アルコールチェッカーの導入です。クラウド型のアルコールチェッカーを導入すれば、アルコールチェックの結果に関する情報を管理する手間を大幅に削減できます。
また、直行直帰で対面で確認できない場合でも、リアルタイムで正しい検知結果を確認できます。そのため、運転者が酒気帯び確認を怠ったり、ごまかしや不正をしたりしないようにでき、本質的なアルコールチェックを行えるでしょう。
関連記事:『アルコールチェッカーとは|種類や選び方、使い方、おすすめの検知器を徹底解説』
ちなみに、弊社のクラウド型アルコールチェッカーを導入いただいている企業様からは、
「簡易型のアルコールチェッカーを使用していた時はアルコールの数値を測ることしかできないため、機器本体を写真に撮りメールで管理者へデータ送信していたため負担でしたが、クラウド型アルコールチェッカーに変えてからは記録する手間や結果確認後の承認作業も大変楽になり現場の負担が大幅に減少しました」
「運転者によって勤務時間が違うので、紙だとタイムラグがあったのがクラウドで楽に管理できるようになりました」
など、さまざまなメリットについてお話をいただいています。クラウド型のアルコールチェッカーを導入することは、確実かつ効率的に法令遵守するにはうってつけの製品です。
参考:導入事例一覧
4.アルコールチェックの運用ルールに関するよくある質問

最後に、アルコールチェックの運用に関するよくある質問と回答を紹介します。
- アルコールチェックは誰が行う?
-
白ナンバー車両のアルコールチェックは原則、安全運転管理者が確認を行います。しかし、安全運転管理者が不在の時や確認が困難な場合は、「副安全運転管理者」もしくは「安全運転管理者の業務を補助する者」が確認を行っても差し支えありません。
「安全運転管理者の業務を補助する者」は、資格要件などはありません。安全運転管理者が選任して、業務を補助するよう指導します。
- 直行直帰時のアルコールチェック方法は?
-
直行直帰で対面でのアルコールチェックができない場合は、電話やテレビ電話など、目視確認に代わる方法で行います。その際、運転者は携帯型アルコールチェッカーを携行し、アルコールチェックを行わなければなりません。
- アルコールチェックを怠った場合の罰則は?
-
白ナンバー車両のアルコールチェックを怠ってしまった場合、安全運転管理者の業務違反となり、安全運転管理者の解任や罰則がある可能性があります。
運転者が酒気帯び運転を行った場合は、運転者本人はもちろん、同乗者や車両提供者にも罰則が与えられます。
また、上記以外のアルコールチェックに関するよくある質問をまとめた記事もありますので、ぜひご覧ください。
関連記事:『【まとめ】アルコールチェック義務化のQ&A|よくある15の質問と回答』
5.まとめ|効率的なアルコールチェック運用を構築する
本記事では、アルコールチェックの基本的な運用ルールやアルコールチェックを効率化させる方法について紹介しました。アルコールチェックの基本的な運用ルールをまとめると、以下の通りです。
- 安全運転管理者を選任する
- アルコールチェッカーを導入する
- アルコールチェックの運用を社内に周知する
- 酒気帯びの有無を確認・管理する
アルコールチェックを怠った場合は、罰則の対象となる可能性があります。運用ルールをしっかりと周知させて、運用体制を構築していきましょう。






