アルコールチェックの確認者は誰?管理方法や業務内容、注意点を解説

2022年4月から、業務で白ナンバー車両を使用する事業者に対して、運転前後に1日2回の目視による酒気帯びの有無を確認(アルコールチェック)することが義務化されています。
そして、2023年12月1日からアルコールチェッカーを用いての飲酒検査が義務化されました。
では、飲酒の有無を確認するのは誰でしょうか?
本記事では、「確認者・管理者」の役割について、以下の点を解説します。
- 「確認者」は誰か
- 「確認者」の実施業務や記録すべき項目
- 「確認者」が運転者本人の場合の対応
目次 / この記事でわかること
1.アルコールチェックの確認は誰が行う?

アルコールチェックの確認は、運送会社やバス会社といったいわゆる「緑ナンバー」事業者においては、運行管理者が実施します。
一方で営業車などの「白ナンバー」事業者においては、基本的に「安全運転管理者」または「副安全運転管理者」が実施します。
しかしアルコールチェック対象者が多く、安全運転管理者や副安全運転管理者の対応が困難な場合、深夜早朝や土日祝の出退勤など確認者がいない場合は「安全運転管理者の業務を補佐する者」が確認しても問題ありません。
「安全運転管理者の業務を補佐する者(補助者)」は事業所内で使用者の選任ができます。補助者の指定に関しては欠格事項や資格要件はなく、届出も不要です。
また、運転者に対するアルコールチェックはコールセンターなどの外部委託(アウトソーシング)であっても差し支えありません。中には早朝深夜帯や土日祝など安全運転管理者や副安全運転管理者の対応が困難な日時に限って外部委託している企業もあります。
ただし、補助者は必要な場合に安全運転管理者の指示を受けられる状態にしておく必要があります。
運転者が酒気帯びを判明した場合は、速やかに安全運転管理者へ報告し、指示を受けるか、安全運転管理者自身が運転を中止させるなど、安全確保のための対応を行います。
安全運転管理者、運行管理者については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:『安全運転管理者とは?選任義務から罰則、業務内容まで詳しく解説』
『運行管理者とは|業務内容や必要資格、安全運転管理者との違いを紹介』
また、外部委託を活用し運用されているオリオンビール株式会社様の導入事例も、ぜひご覧ください。
参考:『導入事例|オリオンビール株式会社』
2.安全運転管理者・副安全運転管理者・補助者の違い

ここでは、安全運転管理者・副安全運転管理者・補助者の以下の違いについて解説します。
- ・業務内容の違い
- ・資格要件の違い
- ・申請方法の違い
- ・罰則の違い
業務内容の違い
それぞれの業務内容の違いは、以下の通りです。
| 確認者 | 業務内容 |
|---|---|
| 安全運転管理者 |
|
| 副安全運転管理者 | 安全運転管理者の上記業務の補助 |
| 補助者 | 安全運転管理者・副安全運転管理者の上記業務の補助 |
資格要件の違い
それぞれの資格条件は、以下の通りです。
| 確認者 | 資格要件 |
|---|---|
| 安全運転管理者 |
|
| 副安全運転管理者 |
|
| 補助者 | 特に資格要件なし |
申請方法の違い
公安委員会への届出の違いは、以下の通りです。
| 確認者 | 業務内容 |
|---|---|
| 安全運転管理者 | 選任日から15日以内に事業所の所轄警察の交通課に届け出を提出 |
| 副安全運転管理者 | 選任日から15日以内に事業所の所轄警察の交通課に届け出を提出 |
| 補助者 | とくに届出等必要なし |
罰則の違い
アルコールチェック対象者の飲酒運転などの違反行為が発覚した際に、安全運転管理者への罰則等はどうなるのでしょうか。実際のところ、チェック対象者の違反行為が発覚した際、安全運転管理者などに対しての罰則は決められていません。そのため、罰則の違いはありません。
ただし、アルコールチェックを怠ると、安全運転管理者の業務違反となります。直接的な罰則はありませんが、公安委員会によって安全運転管理者を解任される、命令違反に対しての罰則が科せられる可能性があるため注意しましょう。
また、そのような違反行為が発覚した場合、会社としての責任は当然あります。そのため、安全運転管理者を設けて、飲酒運転などの違反行為をしっかりと防ぐように努める必要があります。
関連記事:『安全運転管理者制度の義務を怠った場合の罰則について解説!その背景は?』
従業員が飲酒運転などをした際の会社の責任について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:『従業員の飲酒運転(酒気帯び運転)による会社の責任|事例と事故を未然に防ぐ対策方法』
3.アルコールチェックの確認者の実施業務
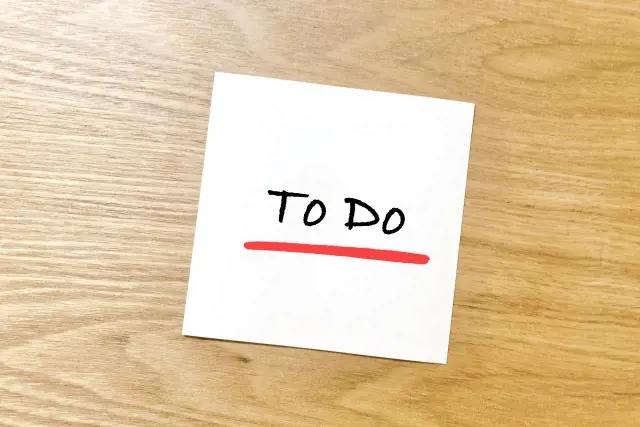
アルコールチェックの確認は原則として安全運転管理者がおこない、安全運転管理者が不在のときは副安全運転管理者や補助者が代わりに実施します。
ではアルコールチェックの確認者は、実際にどのような業務を行う必要があるのでしょうか。
具体的な業務は、以下の4点です。
- ①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認(アルコールチェック)
- ②酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存
- ③アルコール検知器を用いて、運転者の酒気帯びの有無を確認(アルコールチェック)
- ④アルコール検知器を常時有効に保持すること
※①②は、2022年4月から施行、③④は、2023年12月1日から施行されました。
4.アルコールチェックの確認者が記録すべき項目
確認者は、運転者の酒気帯びの有無についての記録を1年間保存しなければいけません。
記録には、下記の8項目が必要です。
| 記録必須の8項目 |
|---|
| 確認者名(点呼執行者) |
| 運転者名 |
| 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号など |
| 確認の日時 |
| どのように確認したか(対面なのか・TELなのか・Webツールを使ったのか) |
| 酒気帯びの有無 |
| 管理者からの指示事項 |
| その他必要な事項 |
アルコールチェック記録簿についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:『アルコールチェック記録簿|項目や記入例、クラウド型検知器で簡易的に実施する方法を紹介』
また弊社では、上記の記録をクラウド上に自動保存することで、確認者と運転者の負担を減らすことができるクラウド型アルコールチェッカーを提供しております。ぜひご覧ください。
参考:『アルキラーNEX|クラウド型アルコールチェッカー【アプリで簡単操作】』
5.確認者が運転者の場合の対応

もし安全運転管理者自身が運転者の場合は、副安全運転管理者や安全運転管理者の業務を補助する者にチェックしてもらうようにしましょう。
6.まとめ|アルコールチェックの確認者が不在時の体制整備も重要
アルコールチェックの「確認者」がどのような業務を行わないといけないのかご理解いただけましたでしょうか?本記事のポイントは以下の通りです。
- 「緑ナンバーは運行管理者、白ナンバーは安全運転管理者」がアルコールチェックの確認をおこなう
- 安全運転管理者不在時には副安全運転管理者、もしくは補助者が確認をおこなう
- 定められた8項目の記録保存をおこなう
アルコールチェックの対応は安全運転管理者や副安全運転管理者はもちろんですが、管理者以外も責任感を持つことが大切です。
さらに、会社全体で協力して飲酒運転をさせないという意識を持ち、しっかりと確認ができる環境を作ることもポイントになります。
アルコールチェックの運用ルールについて詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
関連記事:『アルコールチェックの運用ルール|確認方法や記録項目、罰則などを紹介』






