飲酒による運転への影響|発覚した場合の罰則や対策まで解説

飲酒による運転への影響は計り知れないということは常識として皆様の知るところだと思います。
実際に「飲酒事故を起こして人生終わり」のような話も聞いたことがあるのではないでしょうか。
分かっていても、
「大事な取引先とのアポだから」
「飲み終わってから時間が経っているから大丈夫だと思っていた」
「前日に深酒をしたが、次の日急に朝早くから運転しなければいけなくなった」
など、さまざまな事情や理由があるかと思います。
しかし、飲酒運転はどんな事情があれど言い訳としか捉えられません。
この記事では、飲酒運転を未然に防いで欲しい願いも込めて、実際に飲酒が運転に与える影響や、発覚した罰則、飲酒運転への対策について記載します。ご自身の今後の人生のことをしっかり考えつつご覧ください。
1.飲酒が運転に与える5つの影響

飲酒運転とは、アルコールを含む飲食物を摂取し、アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為を指します。
アルコール成分には脳の神経活動を抑制する麻酔作用があり、理性や判断をつかさどる大脳皮質の活動を低下させてしまいます。その結果、動体視力や判断力が鈍くなり、下記5つの影響が出てしまいます。
- ①ハンドル・ブレーキ操作が遅れる
- ②速度超過の危険がある
- ③視野が狭くなる
- ④車間距離が掴めなくなる
- ⑤蛇行運転の危険がある
①ハンドル・ブレーキ操作が遅れる
アルコールを摂取した状態では判断を司る大脳皮質の働きが低下していることから、急な歩行者の飛び出しがあった場合にブレーキ操作が間に合わないという事態が起こりえます。
また、理性が失われていることから、乱暴なハンドルさばきをしてしまい、運転車両の全損のみならず物損事故や歩行者への激突など重大な事故を起こしかねません。
②速度超過の危険がある
飲酒をすると、気持ちの高ぶりなどによるアクセルを踏みっぱなしにした運転や、判断力の低下によりスピードの出しすぎに気が付かずに運転をし続ける可能性があります。
また、最近の自動車は安全装置なども発達してきていますが、速度超過時は安全装置の作動域を超える運転になる可能性もあります。
③視野が狭くなる
軽めの飲酒であっても、動体視力が落ち、有効な視野が狭くなり検出力が低下すると研究でも判明しています。普段の運転であれば追い越し車両への反応や飛び出しの車両、歩行者に対処できても、視野が狭くなっている状況では対応が追いつかず、車対車の事故や死亡事故につながりかねません。
参考:J-STAGE「運転時の視覚的注意と安全性」
④車間距離が掴めなくなる
停車中の前方車両との距離感覚が掴めなくなり、道路交通法で定められている「直前の車が急停止してもこれに追突しない距離を保持すること」に違反した運転をしてしまう可能性が高くなります。罰則はもちろんのこと、前方車両との衝突や接触事故の可能性は否めません。
⑤蛇行運転の危険がある
ハンドル操作にも繋がりますが、飲酒により体の平衡感覚が乱れているため、直進運転が出来ずに蛇行運転をする可能性が高まります。信号無視や、歩行者の見落とし、カーブを曲がり切れず壁への激突や車両の落下など悲惨な事故が起こりえます。
5つの影響を踏まえてもなお、「自分はお酒に強いから大丈夫」と思われる方もいるかもしれません。ですが、低濃度のアルコールであっても、運転操作に影響を及ぼします。また、お酒に強い人であっても、弱い人と同じようにアルコールの影響が出ることは研究でも明らかになっています。飲酒をして時間が経ってからでも十分注意する必要があります。
以下の記事では、弊社で実際にアルコールチェッカーを用いて、アルコールが抜けるまでの時間を計測する実験を行った結果を紹介しています。
体格や体質によっても違いはありますが、ぜひ参考にしてください。
2.飲酒運転をしたことによる社会的影響とその後の人生
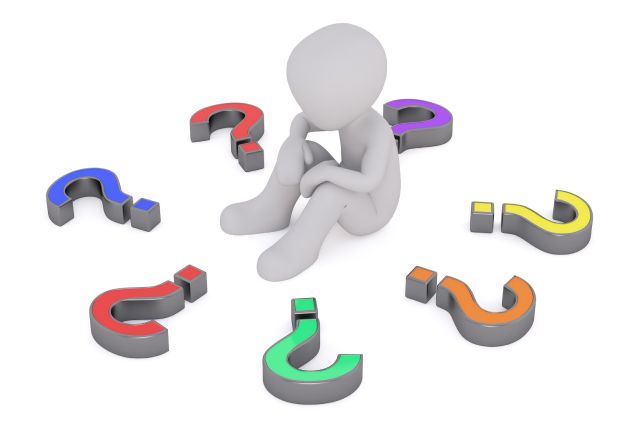
飲酒運転をした場合、どのような社会的影響があるでしょうか。 たとえば、配送ドライバーの飲酒運転が発覚した場合、依頼主や取引先からの信頼を失います。 また、最悪の場合は契約の解除や企業の経営悪化につながり、個人のみならず会社のイメージダウンにも繋がります。
また、飲酒運転による事故で人や車を巻き込んでしまった場合、加害者側の将来だけではなく、被害者側の将来も一瞬にして壊してしまいます。
事故を起こしてしまった後は、事故による入院や治療費などの社会的負担の増加、さらに加害者の解雇で労働力や労働効率の低下など、社会に与える影響が広範囲かつ甚大であることは言うまでもありません。飲酒運転への罰則もあり、 ちょっとした出来心や、ついうっかりと起こした行動が、飲酒運転者の人生だけではなく社会にも大きな影響を与えます。
飲酒運転で事故を起こしてしまった方のその後の人生は大変悲惨なものになります。
以下の朝日新聞の記事では、30代会社員で2人の子供を授かった後に起こしてしまった飲酒運転事故について公開の念を語っています。悲惨さを胸に刻むために一度読んでおくことをおすすめします。
参考記事:朝日新聞デジタル「飲酒事故で人生一変「戻れるものなら」加害者が語る後悔と代償」
3.飲酒運転が発覚した場合の罰則
飲酒運転をしてしまい、その上発覚までした場合の罰則は、主に2つあります。
| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第117条の2第1号) |
|---|---|
| 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第117条の2第1号) |
参考:一般財団法人 岡山県交通安全協会「飲酒運転関係の主な違反一覧表」
酒酔い運転と、酒気帯び運転の違いは下記で解説します。
関連記事でも詳しく記載していますので参考にご覧ください。
関連記事:『酒気帯び運転(飲酒運転)とは|基準や処分・罰則内容をわかりやすく解説』
①酒酔い運転
「アルコールの影響で正常な運転ができない恐れのある状態」のことを指します。
客観的に見て「酔っぱらっている状態」となり、呼気中のアルコール濃度にかかわらず、その場で検挙されます。
②酒気帯び運転
「体にアルコールを保有する状態で運転する」ことを指します。
アルコール検査を実施し、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上で違反となります。
また、運転者だけに留まらず、車両提供者や飲酒運転を下命・容認した者は、酒気帯び運転者と同等の罰則を受けます。さらに、初犯でも裁判にかけられる可能性もあります。
関連記事の『アルコールチェッカー義務化と飲酒や酒気帯びのコト』でも罰則点数などを詳細に記載しています。より詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
4.飲酒運転への3つの対策

罰則のある飲酒運転ですが、絶対に発生しない・させないためにも下記3つの対策を着実に取り組んでいきましょう。
①飲酒したら運転しない
当たり前のことにはなりますが、「飲酒をしたら絶対に運転をしない」という強い意思を持つことが大切です。
本人の意思に依存するものにはなりますが、会社内の考え方ひとつで、従業員の考えも大きく変わってきます。そのため、業務上運転しなければならない状況であったとしても、飲酒をしていた場合には絶対に運転はしてはいけないというルールや考えを会社内で浸透させる必要があります。
業務上の理由で翌日早朝から運転する必要がある場合、前日は一切お酒を口にしないなど飲酒そのもののルールを記載するのもひとつの手だと思います。
②飲酒した人に運転させない
一緒に飲みに行った同僚に自宅まで送ってもらう際も、飲酒した人に運転を強要することを絶対にしてはいけません。飲酒運転が発覚した場合、飲酒運転を下命・任命した人に対しても罰則があります。飲酒した人には車の鍵を渡さないなど対策を打つことができます。
③運転者にはお酒をすすめない
楽しく宴会を過ごすためにお酒を飲んだり、飲ませたりといった行為はどこの企業でもある話だと思います。しかし、最低でも帰宅の際に自宅まで送迎してくれる運転者には絶対にお酒をすすめてはいけません。
近頃開発されているノンアルコール飲料は非常にクオリティが高いので、運転者にはノンアルコール飲料をおすすめしましょう。
みんなで楽しむことを優先しすぎて万が一運転者が飲酒した場合は、運転者もタクシーや公共交通機関を利用し帰宅しましょう。
ノンアルコール飲料を飲んでも運転していいのか?という疑問に答えている記事もありますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:『【危険】ノンアルコールビール(飲料)を飲んで車の運転をしてもいいの?対策と選び方を解説』
ハンドルキーパー運動の推進
ハンドルキーパー運動をご存じでしょうか?
ハンドルキーパー運動とは、「自動車で飲食店へ行った場合に飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、ハンドルキーパーは仲間同士や飲食店の協力を得て酒を飲まずに仲間を送り届けることを任務とする」もので、飲酒運転を根絶するための運動です。一般財団法人 全日本交通安全協会が警察や関係機関・団体の協力を得て、2006年から飲酒運転根絶のために実施しています。
この運動に参加している飲食店では、飲酒運転が発生しないように来店時に車のキーを預かってくれ、飲食後に車のキーを返してくれる取り組みをしています。
参考:一般財団法人 全日本交通安全協会「1. 交通安全思想の普及啓発|(5) ハンドルキーパー運動の推進」
5.まとめ
今回の記事で飲酒による運転への影響は計り知れないということをあらためて知っていただけたかと思います。
下記に今回のポイントをまとめました。
- ・飲酒運転は運転者の認知や判断力を鈍らせ、重大な事故の引き金になる
- ・飲酒運転は社会的な信頼の失墜に繋がりかねない
- ・飲酒運転は罰則も重く、運転者だけの罰則に留まらない
- ・飲酒運転をしない・させないためにも当たり前のことを正しく対策していく
何度も言いますが、飲酒運転は撲滅していかなければいけません。
一人一人の心がけに頼るだけではなく、会社でも飲酒運転をしない・させないようなルールを構築していき、社会から飲酒運転を撲滅しましょう。


