緑ナンバーとは?取得までの3ステップとメリット・デメリットを紹介

街中を走る車の中には、緑色のプレートに白い文字で書かれたナンバープレートを見かけることがあるかと思います。
これは、いわゆる「緑ナンバー」と呼ばれるもので、業務用の自動車に取り付けられるナンバープレートです。
本記事では、緑ナンバーを取得する方法や白ナンバーとの違いに加え、以下の項目について詳しく解説します。
- 緑ナンバーの自動車は他の自動車ナンバーと何が違うのか?
- 緑ナンバーを取得するために必要なことは?
- 緑ナンバーを取得するメリット・デメリット
ぜひ最後までご覧ください。
目次 / この記事でわかること
1.緑ナンバーとは?

「緑ナンバー」とは、どのような車両に付けられるのでしょうか?
また、白ナンバーとは何が違うのでしょうか?
違いについて、詳しく解説します。
緑ナンバーの基本的な情報
緑ナンバーは、軽自動車を除く業務用車両に取り付けられるナンバープレートです。たとえばタクシー・トラック・バスなど、「有償で人やモノを運ぶ車両および事業者」は取り付ける義務があります。
また、緑ナンバーを取り付ける事業は、大きく「旅客自動車運送事業」と「一般貨物自動車運送事業」の2つに分けることができます。
- 【旅客自動車運送事業】
- バスやタクシーなど。道路運送法では、「他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業」と規定されています。
- 【一般貨物自動車運送事業】
- トラックなど。道路運送法では、「他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業」と規定されています。
緑ナンバーを取得するためには「旅客自動車運送事業許可」もしくは「一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)」を取得する必要があります。
参考:自動車運送事業|国土交通省北陸信越運輸局 新潟運輸支局
次章で「一般貨物自動車運送事業」における緑ナンバーの取得方法等について解説しますので、参考にしてください。
緑ナンバーと白ナンバーの違い
緑ナンバーと白ナンバーの違いについて解説します。まず大きな違いとして用途があげられます。
たとえば、他人の荷物を有償で運ぶ場合は「緑ナンバー」となり、自社の荷物を自社の車で運ぶ場合は「白ナンバー」となります。
主な判断基準は、
- 誰の荷物か?
- 有償かどうか?
という2点が緑ナンバーか白ナンバーかの違いです。
2.緑ナンバーを取得するための3ステップ

緑ナンバーを取得するためには、必要な書類の準備や申請などいくつかの手順を踏む必要があります。
本章では緑ナンバーの中でも「一般貨物自動車運送事業」にあたる取得方法の3つのステップについて紹介します。
ステップ1:取得条件の確認と必要書類の準備
緑ナンバーを取得するためには、まず取得条件の確認と必要書類を準備する必要があります。
取得条件として挙げられるのは、以下のような項目があります。
- 営業所
- 車両数
- 事業用自動車
- 車庫
- 休憩・睡眠施設
- 運行管理体制
- 点検および整備管理体制
- 資金計画
- 法令遵守
- 損害賠償能力
- 欠格事由
また、必要な提出書類は、
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
- 運輸開始前確認・運輸開始届
などがあります。ただし、必要書類については地域によって異なりますので、お近くの運輸支局に確認することをおすすめします。
ステップ2:運輸局への申請
緑ナンバーの取得申請に関しては、営業地域を管轄する運輸支局が申請の受付窓口となり運輸局へ申請を行います。
申請するためには必要書類の準備と運輸局で2ヵ月に一度実施されている法令試験の合格が必要です。
運輸局での審査にはだいたい3~5ヵ月ほどかかります。審査が終了すれば許可書が発行され、運輸支局より連絡があります。
ステップ3:車両検査とナンバープレートの取得
運輸局の許可が下りた後は、車両検査とナンバープレートの交付手続きが必要です。
緑ナンバーの交付には登録免許税として12万円、車両1台あたりのナンバープレートの代金として約1,500円、印紙代として350〜500円程度が必要です。
すべての手続きが完了すれば、正式に緑ナンバーでの運送業務が開始できます。
3.緑ナンバーを取得する3つのメリット

緑ナンバーを取得することで、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
この章では、事業運営や信頼性の向上などに関わる代表的な3つのメリットを紹介します。
① 正式に貨物輸送の事業を行うことができる
緑ナンバーを取得することにより、事業者は有償でお客様や荷物を運ぶ正式な許可を得ることができます。
正式に貨物輸送の事業を行うことができるため、顧客からの信頼に繋がります。
② 社会的に信頼度がアップする
緑ナンバーは一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)を取得する必要があります。
厳しい条件をクリアしないと取得が難しいことに加え、運送業許可は国からの許可であるので、緑ナンバーをつけているということは国から認められた事業者となるので社会的信頼度も向上します。
③ 融資を受けやすくなる
先ほども紹介した通り、緑ナンバーは運送業許可を取得する必要があるため社会的信頼度が高まります。そのため金融機関からの融資が受けやすくなります。
4.緑ナンバー取得に関するデメリット

ここまで、緑ナンバーを取得することで得られるメリットについて紹介しました。
一方で、取得には一定の負担や注意点が伴うのも事実です。
この章では、緑ナンバー取得にあたって知っておきたいデメリットについても紹介します。
取得のために初期コストがかかる
先ほどの緑ナンバーを取得するためのステップでも紹介しましたが、緑ナンバーを取得するためには登録免許税として12万円、車両1台あたりのナンバープレートの代金として約1500円、印紙代として350〜500円が必要です。
また、緑ナンバー取得後も、運行管理者の選任や車検など人的コストや物理的コストが発生することになるでしょう。
緑ナンバーの取得までの申請手続きが複雑
緑ナンバーを取得するためには前の章でも紹介しましたが、さまざまな条件や申請が必要です。手続きが煩雑であることから、申請書類の作成や提出代行を行政書士へ依頼するのもひとつの手段です。
5.緑ナンバー取得に関するQ&A
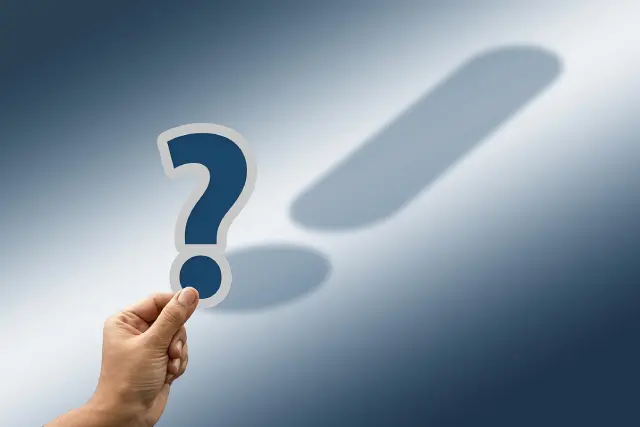
緑ナンバー取得に関してよくある質問について紹介します。
-
個人でも取得できる?
個人事業主でも緑ナンバーを取得すること自体は可能です。
ただし、車両5台以上・ドライバー5名以上が必要など、法人での取得と条件は同じですので少しハードルが高くなります。個人で取得する場合は、「軽貨物運送事業(黒ナンバー)」も検討すると良いでしょう。
-
申請時の注意点は?
緑ナンバーを取得するためには取得条件を満たすことや必要書類の準備であったり、法令試験の合格が必要です。また、審査にかかる期間も3〜5ヵ月と長期間必要となります。そのため、運送業務を開始したいと考えている期間より逆算し、早い段階から申請に向けて準備するよう注意する必要があります。
6.まとめ|緑ナンバーで得られる信頼は手間以上の価値がある
緑ナンバーを取得するまでの道のりには、多くの手続きや準備が必要であり、正直なところ「手間だな…」「大変そうだな…」と感じた方もいるかもしれません。
しかし、その手間をかけてでも取得する価値は十分にあります。なぜなら、緑ナンバーを持つことで、国から正式に認可された事業者としての信頼性が得られ、顧客に対しても大きな安心感を与えることができるからです。
今後、有償での運送事業に本格的に取り組みたいと考えている方にとって、緑ナンバーの取得は避けて通れないステップです。
長い目で見れば、それは事業の安定性と成長を支える大きな投資とも言えるのではないでしょうか。有償での運送事業を検討の際は、ぜひ前向きに緑ナンバーの取得を目指してみてください。






