自動運転の肝であるAI技術と今後の課題|AIの仕組みや開発企業の事例を紹介

自動運転の肝とも言えるのは、車両が状況を判断し適切に運転するためのAI(人工知能)技術です。
近年、日本各地で実証実験や商用サービス化が進み、安全運転支援や渋滞緩和、高齢者や過疎地での移動支援など、さまざまな場面で効果が期待されています。
しかし、自動運転の完全実用化には、AIの認識・判断精度の向上、法整備や倫理課題の解決といった多くの課題が残されているのが現状です。
本記事では、日本における自動運転の現状、AI技術の仕組みや活用例、そして開発企業の事例を交えながら、AIが自動運転の進化にどのような影響をもたらすのかを詳しく解説します。
目次 / この記事でわかること
1. そもそも自動運転とは?各レベルの定義と日本の現状

自動運転は、センサーやカメラ、AI技術を駆使して車両が運転操作を自動的に行う技術のことです。
近年は、日本国内でも導入事例が増え、2021年にはレベル3(条件付き運転自動化)の車が一般向けに販売されました。
現在も自動運転技術の開発は各分野で行われていますが、私たちの暮らしにどのようなメリットをもたらすのか、まだ実感できていない人も少なくありません。
そこで本章では、日本における自動運転への理解を深めるために、自動運転の概要や各レベルの定義について解説します。
1-1 自動運転とは?
自動運転とは、ドライバーによる操作を一部またはすべて自動化し、車両を自動で運転させる技術のことです。
カメラやLiDAR(ライダー)、GPS、AIなどを組み合わせ、周囲の状況を検知・判断してアクセル、ブレーキ、ハンドル操作を行います。
日本の自動運転技術には、運転をサポートするレベルから、完全自動運転を行うレベルまでの計6段階が設けられており、それぞれ運転操作の自動化範囲やドライバーの関与度合いが異なります。
現在の市販車ではレベル2が主流で、一部ではレベル3の自動運転技術も導入され、今後はレベル4に向けて、さらに技術開発が加速する見込みです。
では次に、具体的な自動運転レベルについて見ていきましょう。
1-2 自動運転のレベルは0〜5の6段階
自動運転は、システムが運転操作にどの程度関与するかに応じて、0から5までの6つのレベルに分類されています。
この基準はアメリカのSAE(自動車技術者協会)が定めたもので、国土交通省が日本向けに定義を策定しました。
各レベルの特徴は以下のとおりです。
| レベル | 特徴 | 運転操作の主体 |
|---|---|---|
| 0(運転自動化なし) | 自動運転技術がなにも搭載されていない状態 | 運転者 |
| 1(運転支援) | アクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかが、部分的に自動化された状態。 | |
| 2(部分運転自動化) | アクセル・ブレーキ操作およびハンドル操作の両方が、部分的に自動化された状態。 | |
| 3(条件付き運転自動化) | 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、システムが運転操作の全部を代替する状態。ただし、システムの作動中は運転者はいつでも運転操作を引き継げる状態であること。 | システムと運転者 |
| 4(高度運転自動化) | 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、システムが運転操作の全部を代替する状態。 | システム |
| 5(完全運転自動化) | システムが運転操作の全部を代替する状態。 |
現時点で、市販車はレベル2〜3に留まっており、一部地域や企業では、レベル4の自動運転バスの実証実験や実用化が行われています。
以下の関連記事では、各レベルのより詳しい解説や対象車種、自動運転のメリット・デメリットについて紹介していますので、あわせて参考にしてください。
2. 自動運転を支えるAIの仕組み
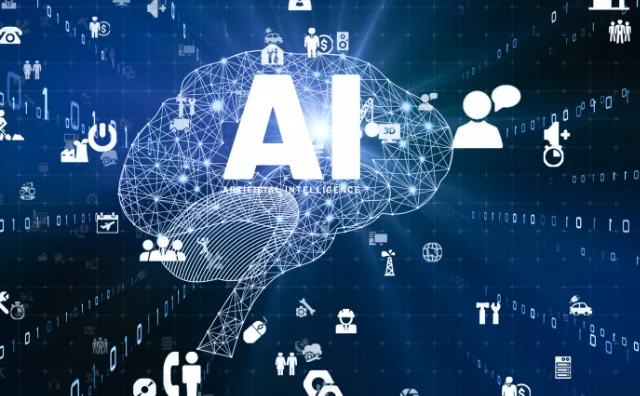
完全な自動運転化には、AI技術の向上が欠かせませんが、そもそもどのように精度を向上させているのでしょうか。
本章では、自動運転を支えるAIの3つの基本的な仕組みについて詳しく解説します。
- ・認知(周囲の状況把握)
- ・判断(走行ルートと運転操作の決定)
- ・学習(走行データからの精度向上)
2-1 認知(周囲の状況把握)
「認知」とは、AIが自動運転の第一歩として、カメラやLiDAR、レーダーなどのセンサーから得た情報をもとに周囲の状況を把握する能力です。
得た情報をもとに、周囲の歩行者や車両、道路標識、信号などを正確に認識し、危険を予測します。
正確な認知がなければ安全な運転判断はできないため、自動運転技術の中でも重要な役割を担っています。
2-2 判断(走行ルートと運転操作の決定)
「判断」は、認知した情報をもとにAIが最適な走行ルートや運転操作を決める能力です。
速度調整や車線変更、停止などの操作をリアルタイムで行い、交通ルールや周囲の状況に応じた安全な走行を行います。
AIの高い判断能力は、自動運転車両の事故防止や交通違反を防ぎ、渋滞緩和などのスムーズな交通社会の維持に役立ちます。
2-3 学習(走行データからの精度向上)
「学習」は、AIが過去の走行データや実際の運転操作を解析し、認知や判断の精度を継続的に向上させる仕組みです。
近年は、機械学習やディープラーニング(深層学習)などのAI技術が進化しており、AIはあらゆる状況に対応できるようになり、特定の状況では認識精度がさらに向上しています。
この学習能力は、自動運転車両の安全性を高め、より高度な自動運転を実現します。
3. 自動運転に活用される5つのAI技術
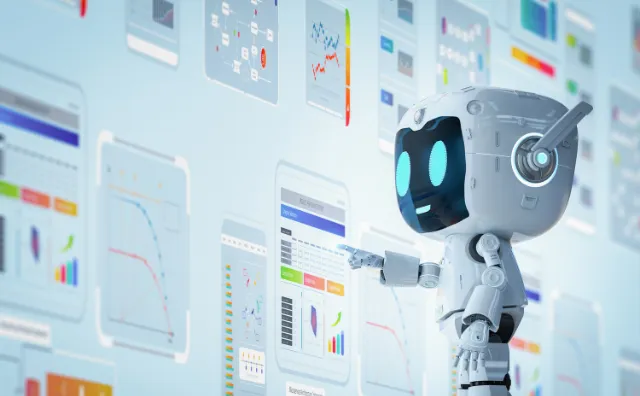
自動運転の普及には、高性能なAI技術の発展・活用が必須です。
自動運転においては、運転中の認知や判断、最適ルートの選択、音声アシスタントによる操作補助や安全管理、さらには交通需要の予測まで、さまざまな領域でAIが活用されています。
そこで本章では、自動運転におけるAI技術の具体的な活用方法を、代表的な5つの分野に分けて詳しく紹介します。
3-1 運転における認知・判断・操作
自動運転車両に搭載されたAIは、カメラやLiDARなどで、周囲の車両や歩行者、信号、道路状況を自動的に認知します。
認知した情報をもとに、最適な走行ルートや車間距離を判断し、アクセルやブレーキ、ハンドル操作を自動で行います。
この認知・判断・操作の一連の流れは、人間の運転行動を再現したものであり、AIを搭載するあらゆる機器に共通して求められる基本的な能力です。
それぞれの精度が向上することで、事故防止や渋滞緩和に役立ちます。
3-2 ルート判断
自動運転では、道路状況や渋滞情報、天候、工事の有無などの情報をリアルタイムで分析し、適切なルートを判断する能力が求められます。
さらに、長距離移動の際に、高速道路を使うか、一般道でゆったり走るかといった運転者の好みまで学習し、最適なルート判断を提案することが可能です。
こうしたAIによるルート判断の精度向上は、物流の現場でも活用できると注目されています。
たとえば、AIが配送順や配送ルートを判断することで、燃料費や労働時間を削減しながら、効率的に利益を確保できます。
完全な自動運転が実現すれば、物流業界の高齢化や人手不足も解消できるでしょう。
3-3 音声アシスタント
音声アシスタントは、車と運転者をつなぐ役割を担っており、運転者の要求に応じて、エアコン調整や音楽再生、電話の発着信などを行います。
移動の快適性を高める上で重要な領域なので、ドライバーの発する言葉を正確に認識し、その意図を理解したうえで運転操作に反映させることが求められます。
ただし、同乗者との会話と、音声アシスタントへの指示を区別する能力も求められており、さらなるAI技術の発展が欠かせません。
3-4 安全運転支援
AIは安全運転を支援する重要な役割を担っています。
カメラやセンサーから取得した情報をもとに、障害物との衝突や車線逸脱、ドライバーの居眠り運転などの危険を検知し、警告音を鳴らしたり自動でブレーキを作動させたりします。
交通事故の多くは注意不足や判断ミスによるものですが、AIによる監視・警告があれば、こうしたヒューマンエラーによる事故を未然に防ぐことが可能です。
さらに、AIはドライバーの運転データを蓄積・分析し、運転スキルを客観的に評価します。
その結果をもとに改善点を提案し、運転の癖を修正するきっかけを提供できるため、運送事業者における安全運転指導にも役立ちます。
3-5 需要予測
タクシー業界では、AIを使って乗客需要を予測する取り組みが進行中です。
車両に搭載されたAIが、運行記録や人口統計、天候、交通状況、イベント情報などを分析し、どの時間・場所で乗客が多く見込めるかを予測します。
今後さらにAIの精度が進化することで、熟練ドライバーの経験や勘に頼っていた効率的な営業が、新人でも可能になり、売上や燃費効率の向上にもつなげられます。
歩合制の給与体系においては収入安定に直結し、離職防止や人手不足解消にも役立つでしょう。
4. 自動運転とAIが直面する3つの課題
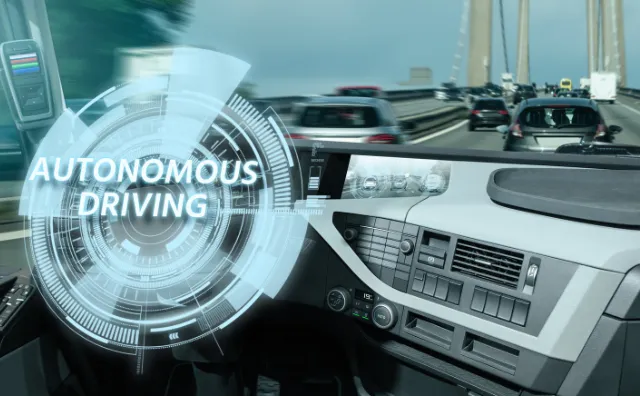
自動運転の普及にはAI技術の向上が課題として残りますが、ほかにも、倫理的・法的な課題も残されています。
そこで本章では、自動運転のAIが直面する技術的・倫理的・法的な3つの課題について詳しく解説します。
自動運転が普及する社会を見据えて、AIとの付き合い方を考えてみましょう。
4-1 技術的課題
自動運転のAIが抱える技術的課題には、「センサーの不完全知覚問題」「運転操作の切り替え問題」「データ処理問題」「セキュリティ問題」の4つが指摘されています。
| 技術的課題 | 内容 |
|---|---|
| 不完全知覚問題 | 「センサーから得られる情報には限界があり、あらゆる状況を判別することは不可能なのではないか」という懸念。AIが誤った判断を下す可能性をゼロにすることが、現状では難しいと考えられている。 |
| 運転操作の切り替え問題 | レベル3における急な運転操作の切り替えに、運転者が対応できないことが原因で事故が起きる問題への対応。「運転者にどうして欲しいのかを、どのように伝えるか」という課題が残されている。 |
| データ処理問題 | カメラやセンサー、ネットワークから得られる膨大な情報を適切に処理する能力が求められている。また、莫大な通信量や情報の処理時間(遅延)の解消といった課題も残されている。 |
| セキュリティ問題 | サイバー攻撃を受けた場合、自動車が制御不能になり事故につながる危険性がある。脅威となるプログラムの判別や、個人情報を守る仕組みづくりが求められている。 |
運転操作の切り替え問題では、実際に切り替え対応の不備が原因となった死亡事故が起きており、「レベル3よりもレベル4の導入を優先した方が良いのでは」という声も出ています。
安全な自動運転の実現には、こうした技術的課題を解決する必要があり、利用者も自動運転の仕組みやリスクを正しく理解することが大切です。
4-2 倫理的課題
自動運転には、事故回避の際に「どのような判断をAIにさせるべきか」という倫理的課題が残されています。
その代表的な例が「トロッコ問題」です。
【トロッコ問題とは?】
「電車の線路上を暴走するトロッコが進む先に、A・B・C・D・Eの5人がいます。
あなたはレバーを動かして別の線路に切り替えられますが、その線路にはFの1人がいます。
この場合、どちらを助けますか?」
という倫理的判断の是非を考える問題です。
自動運転のAIに置き換えると、「車内と車外にいる人のどちらかの負傷が避けられない状況では、どちらを優先するのか」といった問題が考えられます。
負傷する可能性がある「人数」で判断するのか「その人の年齢」で判断するのかなどの基準作りは慎重に行うべきでしょう。
現在も、人命に関わる難しい判断をAIが決めることの是非が議論されており、社会的な合意形成と技術の透明性が求められています。
4-3 法的課題
現行の道路交通法は、人間の運転者を前提として作られているため、新たに自動運転に関する規則の制定や、事故時の責任所在について明確化する必要があります。
AIの誤判断によって事故が起きた場合、メーカーが責任を負うことが主流ではありますが、すべての責任がメーカーに行くのであれば、技術開発や自動運転の普及の妨げになると懸念されています。
5. 分野別|自動運転開発に取り組む国内企業の事例

自動運転の技術開発には、自動車メーカーだけでなく、カメラやセンサーの製造企業、AI開発企業、通信インフラ企業など、さまざまな業界の知識と技術が必要です。
日本でも、それぞれの企業が自社の強みを活かし、課題解決や技術革新に挑戦しており、その連携が日本の自動運転開発を加速させています。
そこで本章では、自動運転の開発に取り組む国内企業の事例を、分野別に紹介します。
5-1 自動車企業
ホンダや日産、トヨタといった国内大手自動車メーカーは、自動運転の基盤技術から市販車への搭載まで幅広く取り組んでいます。
特に、ホンダは2021年に、世界初となる自動運転レベル3を搭載した「レジェンド」を100台限定で販売しており、現在もレベル4の実用化に向けて動いています。
日産は、AIやセンサーの技術融合に注力し、精度の高い安全運転支援技術が評価されているのが特徴です。
トヨタは、圧倒的な技術力と開発リソースを背景に、商業施設やイベント会場での実証実験を積極的に行っており、次世代のモビリティ社会を作る企業として、さらに注目されています。
上記の企業事例の他、自治体では、2025年2月には茨城県日立市で中型バスによるレベル4自動運転が営業運行を開始しています(許認可は2025年1月24日取得)。
参考:ひたちBRTで自動運転バスの営業運行がスタートします!|日立市公式ウェブサイト
また、福井県永平寺町では2023年3月に「ZEN drive Pilot Level4」の認可が取得され、自治体と企業による実証も進行中です。
5-2 カメラ・LiDAR開発企業
ソニーやパナソニックは業界最高解像度となるカメラセンサーを開発しており、夜間でも250mほど先にある物体までの距離情報を画像化する技術を開発しています。
また、京セラや東芝デバイス&ストレージは、光を使って対象物までの距離を測定するLiDARの開発に力を入れており、AIの認知精度や判断精度を向上させる重要な役割を担っています。
5-3 AI開発企業
巴工業株式会社は、AIによる自動運転制御システムの開発に力を入れており、2021年にAIによる自動運転制御システム「CentNIO(セントニオ)」を販売しています。
「熟練の技術者が24時間細やかな運転調整をするのと同じ状況を作り出せないか」といった発想から開発が進み、車両の省電力化やコスト削減を実現しました。
ほかにも、株式会社モルフォは、AIの画像処理性能の開発や、AIの計算処理を高速化するハードウェアであるAIアクセラレーターの開発などに力を入れ、幅広いAI技術を用途に合わせて提供しています。
5-4 AIを活用した自動車の部品検査
自動車の製造現場では、わずかな傷や欠陥も見逃せない厳格な品質管理が求められます。
従来は人の目で一つひとつ検査していましたが、高度な技術を要することから、検査員の育成や人件費が課題でした。
この課題を解決するのが、AI外観検査システムです。
正常品と不良品の大量の画像データをAIに学習させることで、人間の代わりに部品の品質検査を自動化します。
AIは人間の目では捉えきれないほどの微細な異常も、高速かつ高精度に検知できるため、業務効率化や人手不足の解消、検査精度の向上、コスト削減など、多くのメリットが得られます。
上記の事業に取り組んでいる株式会社RistではAI画像検査システム「Deep Inspection」を開発・提供しており、自動車部品の検査分野でも導入事例があります。
たとえば、ホイールの外観検査や自動車部品のX線検査にAIを活用する取り組みを進め、精度の高い不良品検知を実現しています。
また、自動車リサイクル部品の画像診断システムの構築にもAIを活用するなど、自動車産業における多岐にわたる品質管理の課題解決に貢献しています。
5-5 通信技術・インフラ企業
AIが自動運転における頭脳だとすれば、通信技術は神経ネットワークのようなもので、両者がそろってこそ本領を発揮します。
スムーズで安定した通信が実現すれば、AIの情報処理速度や精度が向上し、素早く正確な運転支援が可能です。
ソフトバンクは2017年ごろから、自動運転向けの通信事業を開始し、トラックの隊列走行や車両の遠隔監視、遠隔操作に5Gを活用した実証実験を行っており、現在は自動運転バスの普及に力を入れています。
KDDIは2018年に、自動運転やコネクテッドカーの普及を見越して、落下物情報をLTE(高速携帯電話通信)を活用して、ほかの車両と共有する実証実験に成功しています。
6. まとめ|AIと自動運転がつくる新たなクルマ社会に期待しよう
本記事では、日本における自動運転の現状やAI技術の仕組み、自動運転への活用例や今後の課題、国内企業の最新動向について解説しました。
AIと自動運転技術の進歩は、交通事故の減少や渋滞緩和、高齢者や過疎地域における移動の自由度向上など、私たちの生活に大きな変化をもたらします。
特に日本では、物流業界の高齢化や人手不足といった課題解決にも期待されており、すでに、医療・福祉業界、観光業界にも活用が広がっています。
ただし、レベル5相当の完全自動運転を目指すには、AIの認識・判断精度の向上や法整備を行うことも重要なポイントです。
今後の自動運転とAI技術の発展や、社会での普及状況に注目し、安心して利用できる次世代のモビリティ社会に備えましょう。






